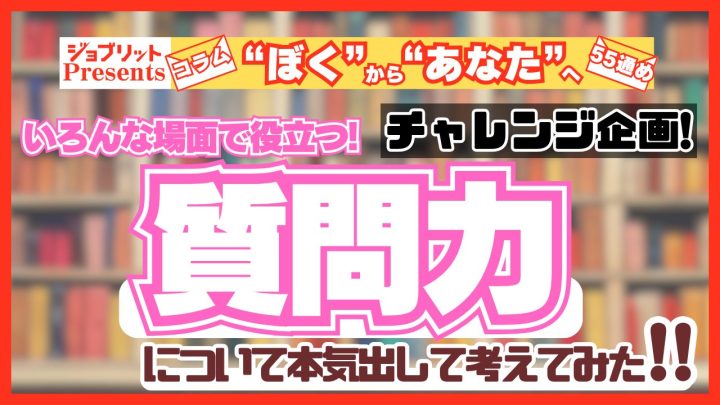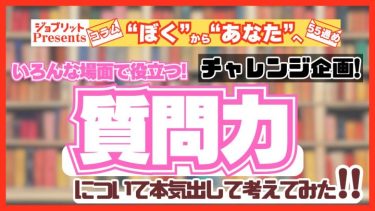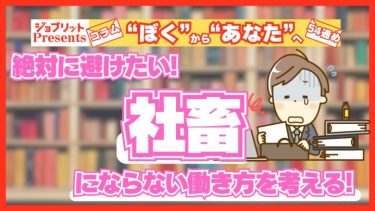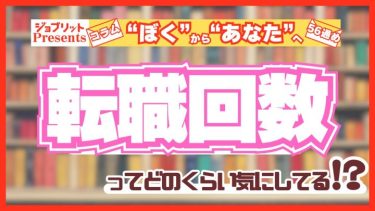ここにたどり着いてしまった“あなた”、こんな言葉を聞いたことがありますか?
『質問力』
正直、ライターという日本語に対して偏屈な仕事をしている“ぼく”にとって、むりやり熟語化したような言葉は好きではありません。
でも、この言葉は社会人にとって、ものすごく必要なスキルだよなと素直に思えます。
そこで今回は質問力について、おじさんライターが真剣に考えてみたいと思います。
質問力ってそもそもどんなスキル?
今回のコラムを進めるにあたり最初に2つ、明らかにしないといけないことがあります。
まず、質問とはなにか。そして、質問力とはなにか。です。
ということで、まずは質問という単語の意味を国語辞典で調べてみましょう。
しつ‐もん【質問】 の解説
[名](スル)わからないところや疑わしい点について問いただすこと。また、その内容。「—に答える」「先生に—する」引用:goo辞書『質問』より
質問力というスキルを解説
ほぼほぼ分かっていたことではありますが、質問という言葉の意味は日本人の99.9%の認識と大差ありませんでした。
では、今度は本題。質問力とはどんな力、スキルなんでしょうか。
さすがに国語辞典にはないでしょうから、google先生のAIさんの回答を載せておきます。
質問力とは、相手に的確な質問を投げかけ、情報や意見を引き出す能力のことです。
単に質問するだけでなく、相手の状況や意図を理解し、より深い情報を引き出すためのスキルです。
これは、コミュニケーション能力の一環として、ビジネスや日常生活において重要な能力の一つとして認識されています。
(引用:Google『質問力 とは』の検索結果より)
要するに、自分が聞きたいことを相手にしっかり伝える力、間違えて受け取られないような質問の仕方ができる力、という感じかな。
ちなみに、このAIの返事を引き出すにあたり、ぼくも質問力を発揮しています。
それが検索ワードに打ち込んだ「質問力 とは」の後半部分、“とは”ですね。
まあ、Google先生の場合、“とは”なしでも概要を引き出すことはできます。今この「AIによる概要」を試験的に運用して、より利便性を高めようとしている最中ですから。逆に、不要な場合でもむりやり出してくるくらいですし。
「質問力」の分かりやすい例
でも、聞く相手が人間だったらどうでしょう?
ぼくがあなたに「質問力!」とだけ言ったら、あなたはどう答えますか?
きっと、すごく勘のいい方でも「あー、すごく大事だよね」と返してくれるのが精いっぱい。ほとんどは「は? 急にどうした? 狂った?」だと思います。
でも「質問力とは?」と疑問形にすることで「質問を相手に的確に伝える力のことかな?」という答えを引き出す確率を上げられますよね。
ただ、この段階でも「あー、大事だよね」という、聞きたい答えとは違う返事をされる可能性は否めません。
そこでさらに「質問力ってどんなスキルだろう?」と付け加えたらどうでしょう。これならほぼ間違いなく、欲しい答えが返ってくるはずです。
かんたんに言えば、リアルタイムでどんどん進行していく会話の中で、常にこういった相手に意図を伝えきる質問ができるかどうか、というスキルのことだと思います。
なぜ質問力が大事なのか
質問力の高さは、いろいろな部分で効果を生みます。
まず、時間の短縮。質問力が高いほど、相手との会話のラリー回数が減ります。ということは当然、時間も短くなります。
これは社会人にはありがたいポイントですよね。特に忙しい(ふりをしている)上司に聞くときなんて、めちゃ有効です。
あと会話の主導権を握れるというメリットもあります。
自分が聞く⇒相手が答える、という流れをキープし続け、会話の流れを自分がコントロールできれば、リアルタイムでどう変化するか分からないコミュニケーションにおいても、ある程度、自分の意図した結論に誘導できるようになる。
これもね、ものすごく大きいですよ。
この部分をさらに突き詰めると、わざと質問力のレベルを下げた質問をして口数の少ない相手に「はい/いいえ」以外の発言を促すというような、高等テクニックを使えるようになっていきますから。
最後におまけとして、人間関係が悪化しにくいという付加要素も紹介しましょう。
分かりにくい質問ばかりしていると、相手はだんだんいらいらしてしまうもの。それに自分の意図を理解してもらえないんだから、あなたもいらいらしちゃうかもしれません。
そんなつまんない理由による不仲を避けられることも、メリットと言えるはずです。
社会人にとっての質問力とは
上で書いたメリットは、ほぼすべて社会人も享受できます。会社でのやり取りを例に挙げた時間短縮はもちろん、会話のコントロールや人間関係も社会人に役に立ちます。
まとめれば、質問力とは社会人にとって高いほどありがたいスキルであると同時に、高いほど周囲に迷惑をかけないマナーでもあるという感じでしょうか。
そして今、この質問力が非常に注目されているのには、大きな理由があります。
それがChatGPTに代表されるAIを最大限、活用するために重要なスキルだからです。
質問力が高いほどAIは力を発揮する
AI。以前、このサイトでも紹介されていましたが、Artificial Intelligenceの頭文字を取った言葉で、日本語では人工知能と呼びます。
皆さんご存じでしょうが、どれだけAIが進化したといっても『ツール』という事実は変わりません。
ツールである以上、人間が上手に指示を出す必要があります。
そして、その指示の出し方がうまいかどうかは、質問力に共通すると個人的には考えています。
上手に指示を出す方法
では、どうすれば指示出しが上手になるのでしょう。
意外とかんたんなことだし、みんなある程度は意識してやっているはずです。でも、きちんと考えたことはないかもしれませんね。
まず、自分が何をしたいのかを明確にイメージします。最終形、ゴールが具体的に見えているほど、ツールは的確に応えてくれます。
次に、ツールにどんな役割を求めるのかを考えます。
最後に、やってほしいことを具体的に説明します。
まあ、言葉にすればこれだけなんですよ(笑)。
でも、特に最後の部分はむずかしいかもしれません。そこで極めてシンプルな例を出してみましょう。
指示出しの具体例
あなたは東京都に住んでいます。今度、高校の同級生5人と集まって食事をすることになり、幹事的な仕事を任されました。
お店探しにAIを活用するとき、どんな風に質問したら的確な答えが返ってくるでしょう?
この場合、抑えておきたいポイントとして下記が思いつくんじゃないかと思います。
(ちなみにあえて1つ、皆さんが忘れそうなポイントを外しています。それが何か、見ながら考えてください)
①営業時間
②立地条件
③予算
④5人が座れる席があるか
⑤みんなの食べたい・飲みたいものが揃っているか
いかがですか? これで充分だと感じますか?
これで調べてみたら、ある程度、希望に沿った候補を提示してくれるでしょう。
でも、すごく大事な要素が抜けていますよね。そう、そのお店が予約できるかどうかです。
このように1つ抜けていると、もう一度作業をやり直さければいけなくなる可能性があります。
そして、これって質問力にも直結していると思いませんか?
だって、AIを活用するための条件づけって、そのまんま事前リサーチが必要な項目なんですから。
あらかじめメンバーに質問を送る。その返答からゴールが見えてくる。そしてその条件を丁寧にAIに伝えれば、1回で理想どおりの答えが返ってくる。
こんな流れなわけです。
質問力を向上させたいならAIを使おう!
ぼく的に、質問力を向上させたいなら、積極的にAIを利用するのがいいと思います。
なぜならAIは所詮、ツールですから。感情を持っていません。あなたがどれだけ質問に失敗しても、機嫌を損ねたり嫌われたりすることはないんです。
だから安心して何度でも練習できます。
深く考えず、AIに聞いてみる。そして期待とは異なる返事をされたら、何が足りなかったかを考えて、先ほどの質問文に不足ポイントを追記してみる。
これを繰り返せば、誰にも迷惑をかけることなくあなたの質問力を大幅に向上させられるでしょう。
今は無料でいろんなAIを使えますから、とにかくやってみてください。
まとめ:質問力の向上=ストレスの低減!
個人的に、質問下手な人にものを聞かれ続けると、ちょっといらっとします。
でもそれ以上に、自分がうまく質問できなかったときのほうがストレスを感じます。だってぼくは取材がメイン業務の1つに組み込まれているライターですから。
本当は聞き上手、質問上手じゃなきゃいけない立場だからこそ、それがうまくできないとストレスがやばいんです。
皆さんも、大なり小なり似たような感覚はあるのではないでしょうか。
ぜひ、AIを練習台にして質問力を向上させて、社会人としてのマナーアップをめざしてください!
| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |