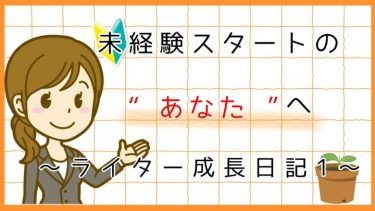前回のコラムで名前を変えました。魔王です。(たぶん)怖くないです。(絶対に)強くないです。(まったくもって)偉くないです。でも、魔王なんです。よろしくお願いいたします。
さて、先週の金曜日(2025年7月11日)から、ぼくの後輩・芽生(めい)ちゃんのコラムがスタートしました。いやあ、とってもめでたい。
それに伴い、ぼくこと魔王くんのコラムの更新日を変更する必要があったので、ついでにタイトルも新たに付け直してみました。
その名前は「かきあたりばったり」。
過去のコラムで複数回、書いたことがありますが、ぼく自身はコラムを書くにあたりプロットと呼ばれる構成案を作らずに書きはじめます。そしておよそ9割くらいの確率で、そのまま勢いにまかせて書き切っています。
つまり書いてみないとコラムがどう転がるか分からない。まさに行き当たりばったりな書きものなので、このタイトルがぴったりかなと。
とはいえ、内容自体は前と変わりません。
いろいろ経験をしてきたおじさんだからこその考えや感じ方も、もしかしたらお若い“あなた”にとって役立つことがあるかもしれない。
そういう発想のもと、いろんなことを書いていきたいと思います。
新人時代のこと、覚えてますか?
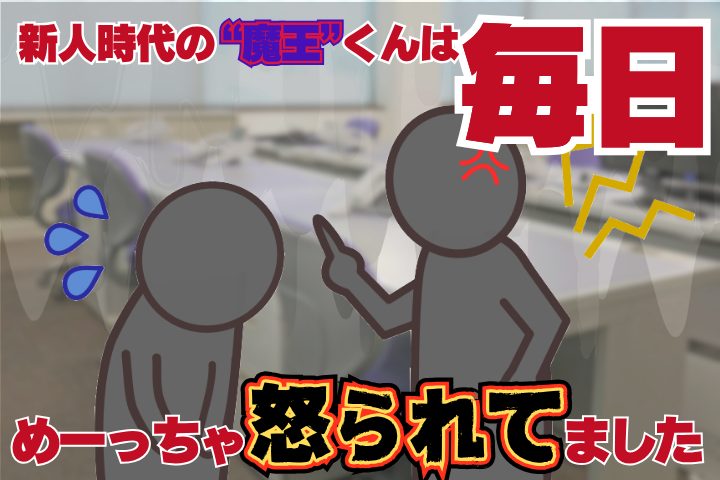
今となっては立派なおじさんのぼくですが、あったんですよ。新人時代ってやつが。当たり前ですけど。
皆さんもそうだったと思うんですが、新人のころって仕事できるわけないですよね。ましてや“THE無能”という称号をもつぼくなら言わずもがな。
人より多く・長く叱られてきたぼくは、新人時代のこともよーーーく覚えています。
そして、新人ちゃんに教えたり聞かれたりするたびに、覚えておいてよかったって思うんです。
“できること”ができない。それが新人だ!
ぼくの場合、ライターというちょっと特殊な職種なんで、エビソーダ()がそのまま、皆さんの参考になるわけではないかもしれません。
でもアウトラインって言えばいいんですかね。「日常生活で当たり前にやっていることさえミスってしまい、そこを先輩に怒られる&呆れられる」みたいな概要は、似ているんじゃないかなと思います。
その昔、小さな雑誌出版社で編集者として文字周りの仕事を始めたころ、いわゆる「てにをは」を頻繁に間違えて先輩にめちゃくちゃ怒られた記憶があります。
そりゃそうですよね。
だって、普段のメール連絡では間違えたりしないんですよ。それがなぜか仕事になった瞬間、小学校低学年レベルまで国語力が落ちるんだから。
でも、こういう現象って、きっと多くの方が体感しているんじゃないかなと思うんです。
経験上「怒る」「叱る」は逆効果!
でね、自他ともに認めるTHE無能なぼくは人よりたくさんミスって、人よりたくさん怒られたわけですよ。
そんな経験を踏まえて、ぼくには1つ確信をもって言えることがあります。
それは「“できることができない”ときに怒るのは100%逆効果」ってこと。
いや、怒られて当然なんですよ。小学生でも間違えないようなミスなんだから。
でもさ、普段ならできるのに、仕事となると急にできなくなる。それって結局、委縮しているだけってことですよね。
怒ることでその委縮が治りますか?
NOですよね。むしろ怒られたことでさらなる委縮を生むでしょう。よりミスしやすい状態に持っていってるんだから、意味ないどころかマイナスです。
逆に“ミスしなくなる”ときってどんなとき?
じゃあ、どうすればミスしなくなるのか。これもぼくは確信をもって答えられます。
それは「自分に自信を持てたとき」です。
ぼくがそうでした。3年くらい、本当に何もできなかったぼくですが、雑誌とはまったく関係のない仕事で結果を残したことによりなぜか自信がつき、そこから急にページづくりまでうまくなりました(当社比)。
ぼくはそれまで「(このページで)何を伝えたいのか分からない」とダメ出しされ続けていました。一応、自分なりに伝えたいことがあったにもかかわらず、です。
結局、ぼくに足りなかったのは“思い切り”だった。
自分に自信が持てないから、伝えたいこと以外の情報にページの分量を割いてしまい、何がメインで何がサブなのかが伝わりくい、中途半端なページを量産していたんです。
それが、まったく関係ない仕事を褒められたことで急に思い切れるようになった。センスとかは皆無でも、伝えたいことをドーン! と大きく打ち出せるようになったんです。
そうしたら、冗談抜きでダメ出しの回数が95%くらい減りました。
サイトと違って紙媒体には載せられるスペースに限りがあります。当然、何かを大きく打ち出せば、載せられない情報も出てきてしまいます。
そこを「載せられなかったものは次号でいい!」と開き直って考えられるかどうか。変わったことはそれだけでした。
先輩の役割とは?
ここまで書けば、もうお分かりですよね。
先輩の役割って、基本を教えることだけじゃないんです。いや、もちろんそれも大事ですよ。だけど、いちばん大事なのはそこじゃない。
それよりも、後輩に自信をつけさせること。
そのために、何度でもチャレンジさせてあげること。
そして、その結果、成功したらきちんと褒めること。
この3つに尽きるんじゃないでしょうか。
逆に言えば、自信をつけてあげないと、いつまで経っても基本は身につかない、もしくは身についても発揮できないと思うんです。
今も当時のことを思い出します
ぼくは当時、教育を担当してくれた先輩とあまり仲良くありませんでした。というか、はっきり言えば大嫌いでした。
それは決して怒られたことへの逆恨みではありません。もっと単純に、性格がまったく合わなかったからです。
でもね、今でもこうやって原稿を書いているときに「あ、気をつけなきゃ!」と思うことって、ほとんどその人から注意された部分なんですよね。
最初にその人に教わってから16年くらい経って、いくらぼくでも「文章とはなんぞや」みたいなことが少しはわかってきました。
それでも気をつけようと思うことは嫌いだった先輩からの注意なんですから……本当に正しいことを教えてくれていたんだなと思います。
ここに関しては心からの素直な気持ちとして、とても感謝しています。
そしてライター未経験の後輩ができた今、改めて強く思います。
今度は自分がそういう先輩にならなきゃいけないんですよね。
……。
うん、無理だな。芽生ちゃん、ごめん!
まとめ:一事が万事
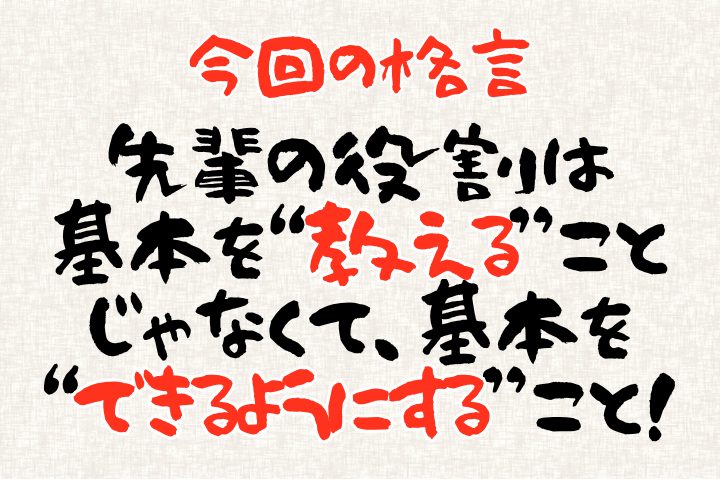
ぼくの好きな言葉にタイトルのようなものがあります。
多くの方がご存じでしょうけど、念のため意味を書いておくと「一つのことが他のすべてのことに当てはまる」。もしくは「一つのことから他のすべてのことを推測できる」てな感じです。
そして、仕事というジャンルにおける「一事」とは、きっと基本だと思うんです。それは職業がライターであれ営業であれなんであれ、共通ではないでしょうか。
でね。芽生ちゃんの場合、ぼくから基本を学ぶわけですよ(笑)。
ちなみに彼女は小説を書きたいという大きな夢を持っているのだとか。
やっと憧れていたライターという職業に就いて夢への第一歩を踏み出した今、彼女はきっと明るい未来を思い描いているでしょう。たくさん勉強して、物書き・文字書きという大きな山を登っていこうと頑張ってくれています。
なのに、教えるのがぼく。
高い山を登り始めたつもりが、実はバンジージャンプ乗り場への階段を上がっているだけだった。挙句、紐なしバンジーさせられた。そんな悲しい未来がありありと目に浮かぶようではありませんか。
ところで。
“ぼくの後輩”というポジションで幸せに生きていくには、1つだけ欠かせない心構えがあるんです。
それは「先輩を信じないこと」。
芽生ちゃんが将来、紐なしバンジーを避けるためにも、誰かこのことを教えてあげてください。切実にお願いします。
「こんなところまで教育を放棄するな!」。
そんな真人間によるお叱りなど聞こえんのだ。すまんな。
| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |