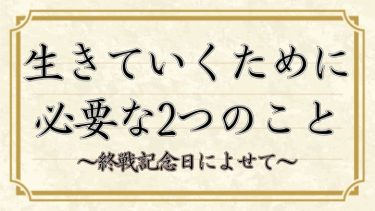「報連相(報告・連絡・相談)」、「時間厳守」など、社会人として守るべきルールの数々。それらの多くは守って当然のものですが、それとは別に特定の組織・グループ内でのみ運用されるローカルルールも存在します。
そして、その中でも業務効率を低下させたり、社員にストレスを与えたりするものが“謎ルール”。そんな目的も効果も意味も不明なルールによるストレスが、セクハラやパワハラといったハラスメントの原因となってしまうこともあるのだとか。
今回はそんな謎ルールの実例と対策について解説していきます!
謎ルール、その言葉の意味と背景

この記事を開いている方は、多かれ少なかれ謎ルールに対して疑問や不満を抱いているのではないでしょうか。
なぜ謎ルールは存在するのか。そして、存在意義はあるのか。
それを考えていくため、はじめに謎ルールとは何かを説明していきます。
謎ルールとは?
謎ルールとは、どうして存在しているのか、どういった効果をもたらすのか、まったく理解できない決まりのこと。
ほとんどの場合、会社や学校、仲間内のグループなど特定の組織でのみ有効となる、ローカルルールでもあります。
ここまでは、みなさんの認識と大きく違った点はなかったでしょう。
存在の背景
ここまでの紹介で、もうすでに「謎ルールはなぜ存在するのか」という疑問が浮かんできたのではないでしょうか。
Googleをはじめとした各種インターネットサイトを調べたところ、以下のような理由が目立つようです。
・慣習や伝統
・権威主義
・同調圧力
・情報不足
ここからは、上記4項目を1つずつ解説していきます。
慣習や伝統
1つめの理由は、会社に根づいている古くからの慣習や伝統が、現在にいたるまで受け継がれているというもの。
ルールとして機能した期間が長いほど固定化されやすいことから、創業からの歴史が長い会社で特に目立ちます。
歴史を重んじることはもちろん大切ですが、働きづらさを生んでいるのなら思い切って見直すべきかもしれません。きっと会社内の雰囲気の改善につながるでしょう。
権威主義
2つめは、社長や部長など、権力のある人間の意向が優先されるというもの。
ルールに異議をとなえても、その意見が潰されてしまった。そんなパターンもここにあてはまると考えられます。
権力社会が薄まりつつある現代でもよくある話ではないでしょうか。
同調圧力
3つめは、多くの人間が従っているから、自分も従わなければいけないと思い込んでしまうというもの。
たとえ疑問を感じていても、周囲がそれをよしとしているからと従ってしまう。
これは年齢や世代を問わず、身に覚えのある方も多いのではないでしょうか。
情報不足
最後は、最新のルールについての情報が不足していることによるもの。
昔は正しかったルールでも、時代の変化によって正しくなくなってしまうことがあります。
そして、最新の情報にアップデートできていないと世間一般のルールから乖離してしまい、“謎ルール”と呼ばれることになってしまうのでしょう。
謎ルールの実例
ここからは謎ルールの実例を紹介していきます。
自分が勤める企業にも同じようなルールがないか、ぜひご確認ください。
37種の謎ルールをイッキ見
・育休を取ると昇進に影響する
・休暇中の旅行は行き先を伝える
・休憩時間中もできる仕事をしなくてはならない
・業務連絡には、休日や夜間でも反応しなければならない
・子どもがいると、責任のある仕事を任せてもらえない
・始業時間の前に社内を清掃する
・時短勤務をすると評価が下がる
・上司からの誘いは断れない
・上司よりも先に帰ってはいけない
・上司よりも先に出社しなくてはならない
・女性はお茶出しをする
・女性は結婚と同時に退職を勧められる
・女性は出社時、化粧をしなくてはならない
・女性はストッキングを着用する
・女性は送別会などの際、花束を渡さないといけない
・女性はメガネ禁止
・女性や若手は宴会の席で気を配らなくてはならない
・女性や若手は会議室のリセット作業をする
・女性や若手はコピー用紙など、備品の補充をする
・女性や若手はゴミの回収や給湯室の清掃をする
・女性や若手は手土産や贈答品、出張土産の配る
・誰かの仕事が終わらないと、連帯責任で全員が残業を強制させられる
・男性しか管理職になれない
・男性は育児より仕事を優先すべき
・男性は家族を養うため、優先して昇進させられる
・男性は子どもがいても長時間労働をしなくてはならない
・男性は深夜残業をしなくてはならない
・男性はスーツで出社しなくてはならない
・男性は外回りの際、車の運転をしないといけない
・朝礼で意味不明なスローガンを叫ばされる
・妻は夫のキャリアを優先しなければならない
・忘年会や新年会などの飲み会、社内行事は強制参加
・メールの返信がなければ「承知した」とみなす
・有給休暇取得の際は理由を伝えて、許可を得なくてはならない
・若手はみんなの分の義理チョコを配る
・若手は忘年会の幹事を担当する
この中から気になるものを何種類かピックアップして解説します。
育休を取ると昇進に影響する
最近では女性だけでなく、男性も育児休暇の取得が推奨されていますが、一方で育児休暇を取ることによって昇給や昇進に悪影響を及ぼすという声が聞かれます。
しかし、『育児・介護休業法』第10条で下記のように定められています。
上記のとおり、育児休暇の取得を理由に昇給や昇進を見送ることは、法律違反となります。
また、時短勤務という勤務形態を選んだという事実で評価を下げることも同様。
心当たりがある方は一度、弁護士事務所の無料相談の利用をお考えください。
上司よりも先に帰ってはいけない
自分の仕事は終わっていて残業する理由がないのに、上司が仕事を終えるまで帰れない。
これは上下関係が厳しい企業にありがちなルールではないでしょうか。
実際、上司が新人だった昭和の時代には「上司より先に帰るのはいけないことだ」という価値観が常識とされていました。しかし、現代においては定時退社は当然だという考えが一般的になってきています。
そもそも残業を強制させる権利は上司にも会社にもありません。同じように「上司よりも先に出社しなければならない」と命令する権利もありません。
さらに言えば、上司から直接「俺の仕事が終わるまでは帰るんじゃないぞ」と言われれば完全なるパワハラです。
にもかかわらず、なぜ多くの人間がこんな根拠も効果もない“謎ルール”に従ってしまうのか。
その根底には“部下の(一方的な)気遣い”や“職場内の雰囲気”があると考えられます。実際、先ほど解説した同調圧力と同じように「暗黙の了解で残業している」という方も少なくないのではないでしょうか。
もし、この記事を読んでいる方の中に、周囲の空気を読んだ結果、帰れなくなってしまったという方がいれば、一度だけ勇気を出して上司より先に帰ってみてください。
女性はお茶出しをする
総務や経理を含む事務員の女性に任されがちな業務の1つがお茶出し。
男女問わずできる仕事にもかかわらず、なぜ女性だけがお茶を出さなければいけないのか。当事者ならずとも疑問に感じるのではないでしょうか。
来客時の対応は男性が、お茶出しは女性がそれぞれ担当する。
一昔前のドラマでよく見かけたシーンですが、実際は『男女雇用機会均等法』により必要な場合を除いて男女間で業務内容の差別をしてはならないと定められています。
それでもなお、女性のみに特定の業務を任せるという企業は後を絶ちません。これも現代日本が変えていかなくてはならない現象と言えるでしょう。
忘年会や新年会などの飲み会、社内行事は強制参加
新型コロナウイルスの影響もあり、忘年会や送別会に代表される社内行事は減少傾向にあります。とはいえ、未だにそれらのイベントを残している、もしくは復活させている企業も少なくはありません。
そして、これらへの参加を強制された経験をお持ちの方も多いでしょう。
しかし、厳密に言えばこれも法律違反。
社内行事を企業による業務の一環としておこなうのであれば参加する義務はあるものの、その場合は当然、“就業時間中に開催”されなければなりません。
逆に言えば、終業後に催される行事に対して参加を強制する権利は誰にもないということ。
世の中の“経営陣”の皆さん、どうしますか?
休暇中の旅行は行き先を伝える
今ではかなり少数だろうと思うものの、休暇中の予定や宿泊先を上司や会社に報告しなければいけない。そんな謎ルールが残っている会社もあるかもしれません。
しかしこれは、現代を生きる人にとっては“謎”でも、昭和時代には“必要性”を伴っていたルールだったのです。
皆さん、休暇中に緊急事態が発生したら、どうしますか?
スマートフォンがある現代では、いつ・どこにいても連絡が取れます。しかし、つい30年ほど前までは、そんな便利な道具はありませんでした。都会に多く設置されていた公衆電話も、地方や自然の多い観光地に行けば見つけることは困難だった時代のことです。
そんなとき、社員と連絡を取るもっとも確実な方法が“宿泊先のホテルへの電話”でした。
そのため、休暇中に万が一の事態が起きても連絡を取れるよう、行先や宿泊先を会社に伝えておく必要があったんですね。
もし現代でもこのようなルールを残している会社があれば、ほぼ確実にその名残りと言えるでしょう。
このように、謎とされるルールの一部には、“昔は必要だった”ものもあった。そのことだけ抑えておいていただければ幸いです。
補足
念のために書いておくと、連絡をするのは本当に“万が一”のときだけ。
たとえば社長や上層部が亡くなったとか、“大震災”と呼ばれるレベルの自然災害とか、そういったものに限られていました。
そもそもGPSやSNSなどとは無縁な時代で、今よりプライベートに干渉する方法がなかった時代だからこそ、伝える側にも抵抗感がなかったことを追記しておきます。
どうすればいいの?謎ルールの対処方法!
今回、37個も紹介した謎ルール。その多くには共通点が1つあります。
それは「法律に違反している」という点です。
ということは、“あなた”と同じように「なんでこんなルールがあるんだろう?」と違和感を持っている方も多いはずです。
同じ意見を持つ仲間と一緒に声を上げることで、謎ルールを変えるための活路が拓けるかもしれませんよ。
一度、話をしてみよう
実は、違和感を持ってるのは部下・後輩世代だけではないかもしれません。
上司と呼ばれる人たちは就業期間が長い分、若手よりも謎ルールの被害を受けてきた可能性があります。ということは、持っている違和感も大きい可能性があります。
同じように謎ルールに悩み、苦しみ、もがいてきた。
それなのに、なぜ今に至るまで謎ルールが残っているのか。
きっと、上司と部下が協力して謎ルールをなくそうと動かなかったからではないでしょうか。
同じように嫌な思いを経験している上司と部下。きっと分かり合えるはずです。
一度、しっかりと本音を交えて話し合ってみませんか?
上司から見ても、謎ルールがあって面倒なことはあっても、得することなんてないんですから。
まとめ:働きやすい環境を整えよう

謎ルールは会社が定めたものではなく、そこで働く人間が勝手に作ったものです。
若手の方、勝手な忖度、していませんか? 上司の方、意図せずとも忖度させるように圧力をかけていませんか?
話し合ってみなければ、現状を変えることはできません。
逆に言えば、上下関係にとらわれず協力することで無駄なルールは必ず変えられます。
せっかく働くなら、上司も若手も気持ちよく働ける環境を整えたいですよね。
みなさんも今回紹介した対処方法を参考に、謎ルールにしばられない、平和な環境を築いていきましょう。