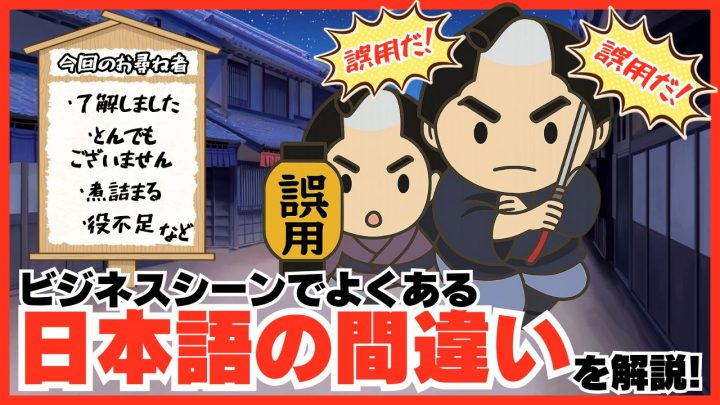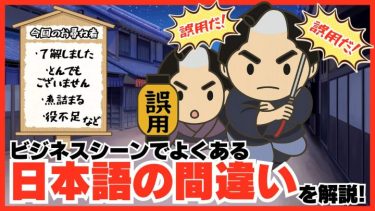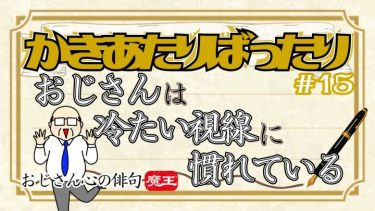日本語はとても難しい言語です。3種の文字を使い分ける必要があり、漢字には複数の読み方があるうえに、同音異義語や同訓異字、似形異字(じけい・いじ。似ているが違う漢字)も多い。
しかし社会人たるもの、正しい日本語を使えたほうが好印象を与えやすいのも事実です。
そこで今回は雑誌編集や求人媒体の取材・原稿作成を通算17年ほどやっている“プロライター”の筆者が、ビジネスシーンで見かける間違いやすい用語の正しい意味や読み方を解説いたします。
すでに社会で活躍している方はもちろん、これから社会人になる高校生、大学生の方も、ぜひ参考にしてください。
誤用・誤読を避けるメリット

友人・知人との付き合いが中心だった学生生活と比べて、上司や先輩、取引先の関係者など、上下関係を意識した人付き合いをしなければいけません。
そんな中、重要になる要素の1つが「教養」。関係性が遠いほど、教養の有無が人間関係構築に大きく影響します。
教養とはひけらかすものではなく、ふとしたときにポロっとこぼれ落ちるもの。
ぜひ本記事をきっかけに、“正しい日本語”を意識していただければ幸いです。
誤用しやすい日本語
煮詰まる
議論や意見が出尽くして、もうすぐで結論が出る状態のこと
新たなアイディアが出ず、先に進まなくなってしまった状態のこと
頻繁に間違われる、誤用の代表格。
誤用のような場合は「行き詰まる」という言葉を使います。
役不足
自分の能力に対して、役が軽すぎること
自分の能力に対して、役が重すぎること
こちらも間違われることの多い言葉。
重要な案件に対して「私には役不足です」と断ると、どれだけ自信過剰なのかと疑われかねないので、注意しましょう。
折衷案
いろいろな意見のいいところを取り入れること
妥協した案こと
いろいろな人の意見の「いいとこどり」することであり、ネガティブな意味は含みません。
確信犯
政治的、宗教的な信念に基づいて正しいと信じて行う犯罪のこと
悪いと分かっていて行う犯罪のこと
本来の意味は「正しいと信じている(罪の意識がない)」、誤用は「悪いことだと分かっている(罪の意識がある)」というのが違い。
文化庁の調査によると、約7割の人が誤用の意味で使っているのだとか。
情けは人のためならず
情けをかけると、回りまわって自分に返ってくること
その人のためにならないので情けをかけないほうがいい
古典に出てくる「ならず」という言葉を、“ならない”ではなく“じゃない”と訳せば理解しやすいかもしれません。
にやける
男性が女性のように、なよなよした態度をとること
にやりと笑うこと。薄笑い
漢字に直すと「若気る」と書きます。語源は…とてもここには書けませんので、ぜひご自身で調べてください。
目上の人に使うのは不適当な日本語
了解しました
上位者が下位者に対して使う用語のため
承知しました
ご苦労様です
上位者が下位者に対して使う用語のため
お疲れ様でした
なるほどです
感嘆詞に丁寧語をつけるのは日本語として不適当のため
おっしゃるとおりです
参考になりました
本来の意味は何かを決めるときの手がかりや材料(の1つ)にすることという意味。目上の意見の扱い方としては不適当
勉強になりました
すみません/すいません
フランクな表現のため
謝罪時…申し訳ございません
呼びかけ…恐れ入りますが
~ください
本来は丁寧な依頼表現。丁寧ではあるが、そもそも目上に対しては「依頼」ではなく「お願い」をするべきのため
ご確認ください…ご確認をお願いいたします
資料を送ってください…資料をお送りいただけますでしょうか
とんでもありません/とんでもございません
「とんでもない」という形容詞の一部だけを切り離して丁寧語にするのは不適当のため
(※同じ理由で「滅相もありません/ございません」も不適当)
恐れ入ります
取り急ぎご連絡いたします
カジュアルな表現のため
まずはご連絡申し上げます
よろしくお願いします
カジュアルな表現のため
よろしくお願いいたします
お手数ですが
相手に手数をかけさせることが分かっているなら、より丁寧な表現にするため
お手数をおかけいたしますが
誤読しやすい漢字①
あり得る
ありうる
ありえる
「あり得ない」という否定形の読みは「あり“え”ない」が正解
年俸
ねんぽう
ねんぼう
“木へん”の「棒」という字と見間違えがちですが、職務に対して受け取るという意味の「俸」です
職人気質
しょくにんかたぎ
しょくにんきしつ
「気質」には“かたぎ”と“きしつ”、2つの読み方がありますが、前者は『職業や身分、地域など集団特有の性格・性質』、後者は『個人が生まれ持った性格・性質』と、異なる意味を持ちます。職人気質の場合、職人という集団によくみられる性格・性質を指すため、“かたぎ”と読むのが正解です
遵守
じゅんしゅ
そんしゅ
“しんにょう”のない「尊」という字と見間違えがちですが、法則に沿って従うという意味の「遵」です
一段落
いちだんらく
ひとだんらく
似た意味を持つ「一区切り」の読みは「“ひと”くぎり」なので注意
汎用
はんよう
ぼんよう、ほんよう
“さんずい”なしの「凡」の字との読み間違えに注意
反故
ほご(もしくは“ほうご”)
はんご
江戸時代は「ほうぐ」と読むのが一般的だったほか、「ほんご」、「ほんぐ」、「ほぐ」とも読まれていたそうです
暫く
しばらく
ようやく
「ようやく」は漢字で「漸く」と書きます
役務
えきむ
やくむ
「役」の字はこのほか「現役(げんえき)」や「使役(しえき)」などで“えき”と読みます
言質
げんち
げんしつ、ごんしつ
「質」の字には“保証する”という意味があります
偏に
ひとえに
へんに
「偏」の字には“かたよる”や“ひたすら”などの意味があります
押印
おういん
おしいん
「押」の字の音読みは“おう”で、「押下(おうか)」などとも使います
奇しくも
くしくも
きしくも
古い言葉で“不思議な”、“めずらしい”などの意味を持つ「奇し(くし)」から生まれた言葉です
誤読しやすい漢字②「慣例読み」編
最後に紹介するのは「慣例読み」と呼ばれる、間違った読み方が定着しつつある漢字たち。
“正解を知ったうえで、敢えて一般的な読み方を用いる”のか、それとも“正しい読み方を知らずに使う”のか。
ここに分類される漢字こそ、まさに教養が試されるポイントだと言えそうです。
代替案
だいたいあん
だいがえあん
“ほとんど”、“おおよそ”などの意味を持つ「大体(だいたい)」との混同を避けるために誤読が広まったと考えられます
吹聴
ふいちょう
すいちょう
「吹」の字には“すい”という読みがあることと、「ふ」の音が「す」よりも発音しにくいにことで誤読が広まったと考えられます
造詣
ぞうけい
ぞうし
「詣」の字は学校で習わないため馴染みが薄く、つくり(この字の場合、右側)の「旨」やそれを用いる「指」に“し”の読みがあることから誤読が広まったと考えられます
世論
せろん
よろん
明治期には“よろん”と読む「輿論」という言葉が一般的であったため、学術的、政治的な意見は「よろん」、世間一般の意見は「せろん」と読み分けられていました。しかし「輿」の字が表外字となり使われなくなった現代では読み分ける必要がなくなったことが原因と考えられます。
ちなみに選挙前などに実施される「世論調査」はもともとの意味から“よろんちょうさ”と読むことも、誤読が広まった要因かもしれません
続柄
つづきがら
ぞくがら
「つづき」という音が発音しにくいことと、「ぞくがら」のほうが短いことから誤読が広まったと考えられます
免れる
まぬかれる
まぬがれる
「まぬ“か”れる」よりも「まぬ“が”れる」のほうが発音しやすいために誤読が広まったと考えられます
重複
ちょうふく
じゅうふく
「破擦音」と呼ばれる“ち”から始まる音が発音しにくいために誤読が広まったと考えられます
過不足
かふそく
かぶそく
「か“ふ”そく」よりも「か“ぶ”そく」のほうが発音しやすいために誤読が広まったと考えられます
異にする
ことにする
いにする
「異」の読みには“い”と“こと(なる)”があるが、送り仮名をつけない場合“い”の読みの方が多いことから誤読が広まったと考えられます
まとめ:日本語は美しい!

まえがきに書いたとおり、日本語は日本人からみても難解な言語です。
ただ、その日本語の読み書きを生業にしているライターの筆者にとっては、これ以上ないほど魅力的な言語でもあります。
その理由は「複雑だからこそ、使いこなせれば美しい」のだと考えています。
皆様も本記事を参考に、仕事で、プライベートで、美しい日本語を使えるように、少しだけ努力してみてはいかがでしょうか。
| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |