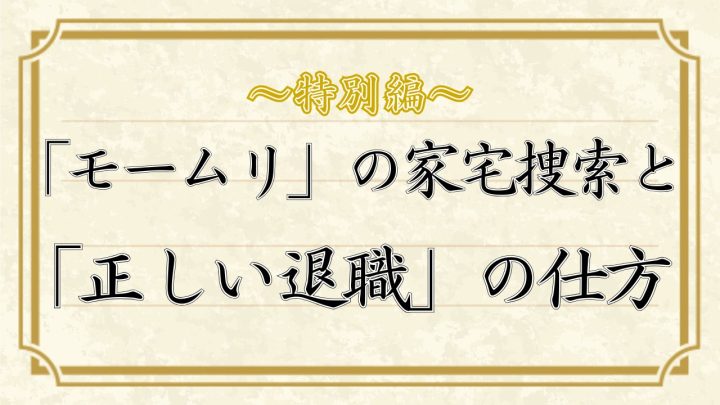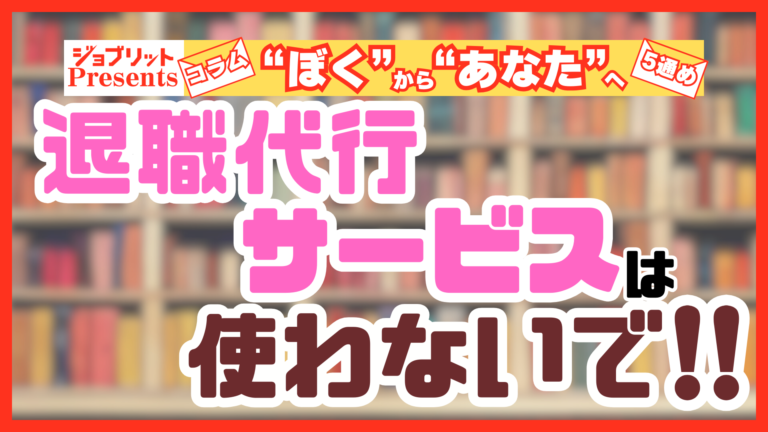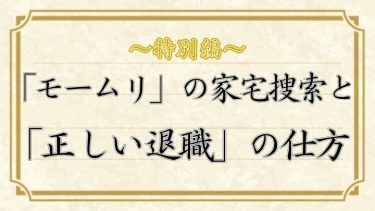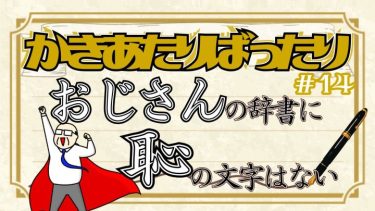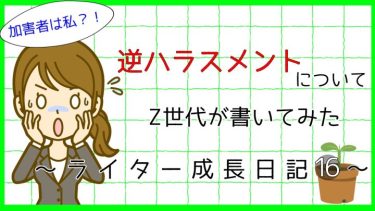ひと昔前のYouTube風に書くなら、今、緊急で原稿を書いているんですけど、という感じでしょうか。
今日、2025年10月22日、こんなニュースが流れました。
>読売新聞オンライン『退職代行「モームリ」を警視庁が捜索、報酬目的で顧客を弁護士に紹介した非弁行為容疑』
【読売新聞】 退職手続きの代行を依頼された顧客を弁護士に紹介し、違法に手数料を得ていた疑いがあるとして、警視庁は22日、…
>産経新聞『退職代行「モームリ」の運営会社を弁護士法違反容疑で家宅捜索 警視庁』
>共同通信『退職代行「モームリ」捜索 弁護士に違法あっせん疑い』
(※並びは配信時間順)
今回の家宅捜索、かんたんに解説するなら「警視庁は10月22日、退職代行サービス『モームリ』を運営している株式会社アルバトロスを“非弁行為”容疑で家宅捜索した」ということ。
これを書いているぼくこと“魔王”は、過去に何度も退職代行サービスについて書いてきました。そして、その1回めとなる昨年5月の記事で警鐘を鳴らしていたので、正直な感想は「ついに来たか……」という感じです。
>あまりおすすめできない退職代行!サービス範囲は?違法性は?
哀しいことに、最近、存在感を増している退職代行サービス。でも、できれば使わないでほしいんです。じゃあ、どうすればいいの?…
ただ、あくまで現段階では「容疑」。つまり、疑われている状態でしかありません。
本当に急遽、書いているこのコラムは退職代行サービスを否定したいわけでもないし、アルバトロスが悪徳行為をしていたと断じたいわけでもありません。
本稿の目的は、まず。「非弁行為」というワードの解説。
そしてもうひとつ。この事件をきっかけに、退職代行サービスが使えない、使うのをためらうとなったときに、どうすればいいのか。正しい退職の仕方について書いていきたいと思います。
非弁行為とは
非弁行為をかんたんに解説すると、「弁護士資格を持たない者が、弁護士にしか許されていない業務を行うこと」。
この項目では、退職代行利用時に直面しやすい非弁行為と、今回の容疑を解説します。
ちなみに。
ぼくは求人周りの仕事を通算7年くらい携わっているのである程度の知識はあるものの、ぼく自身が弁護士資格を持っているわけでもないし、特別な教育を受けたわけでもありません。
ここから先、「~可能性がある」「一般的には~」などの表現が多くなることをあらかじめご了承いただければ幸いです。
“退職”における非弁行為の代表例
通常、退職する際にはいろいろな「事後処理」が必要です。それは業務の引継ぎだけではなく、貸与品(PCや社用スマホ、制服など)の返却や残っている有給休暇の扱い、(未払い分を含む)給与や退職金の減額交渉なども含まれます。また退職後に離職を証明する退職証明書/離職票や社会保険・年金の資格喪失届、源泉徴収票など各種書類の発行も必要になります。
このうち、業務の引継ぎにかんしては法的な拘束力はありません。慣例上、どの企業/退職者もやっていることが多いものの、拒否も可能です。よって、今回の事件にはほぼ、関係ないと言えます。
しかし、貸与品の返却や有休消化についての「交渉」、給与・退職金の減額などの「交渉」、さらに各種書類の発行の「交渉」は、すべて弁護士資格を持つ人間が行う必要があります。
ここで面倒なのが、わざわざカッコ書きにした「交渉」がアウトというところ。
単に退職者の代理人として「依頼」するだけであれば非弁行為にあたらないと判断されるケースが多いようです。
“やらなければいけないこと”をきちんとやってくれる会社であればあまり問題になりませんが、一方で嫌がらせのように遅らせる企業があるという声が聞こえるのも事実。
そうなった場合、退職代行を「業務」として有償で請け負っている代行サービス会社が困っている利用者に「非弁行為にあたるかもしれないから、ここから先はできません」と言えるかどうか。
そうなると、代行側にやれることは2つに1つ。
非弁行為と分かっていながらやってしまうか、それとも弁護士事務所に依頼してやってもらうか。
ただ、ここにも大きな問題があるんです。
非弁行為の成立要件
弁護士法第七十二条をご覧ください。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
過去の判例を確認すると、弁護士資格のない人間が「報酬を得る目的」で弁護士を紹介・斡旋することもこの72条に引っかかるとされているんです。
そして今回、アルバトロスが家宅捜査をされたのは、まさにこの部分なんですね。
実際の容疑
容疑をもっとも詳しく掲載していたのは読売新聞なので、そちらを引用します。
捜査関係者によると、同社の社長は弁護士資格がないにもかかわらず、提携する弁護士に退職を希望する顧客を報酬目的で紹介した疑いが持たれている。警視庁は、同社が法律事務所から違法に紹介料を受け取り、顧客の勤務先との交渉を取り次いでいたとみている。
同法は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務をあっせんし、弁護士が無資格者から顧客の紹介を受けることを禁じている。
はい、まさしく上に引っかかっていますね。
こうなると、「モームリ」をはじめとする“弁護士資格を持たない”退職代行サービス会社にできることは相当に限られると言っていいでしょう。
今後の推測
これは完全なる推測です。
今回、「非弁行為」の1つとして条文でしっかりと規定されている「有償での紹介・斡旋」で家宅捜査を行いましたが……その結果次第では他の行為も見つかるかもしれません。
正直、どこからどこまでを非弁行為(条文によるところの“法律事務”)にあたるかは、解釈次第という部分も大きいので、定かではありません。
ただ過去の判例からすると「各種書類発行に対する交渉」や「(未払い分を含む)給与・退職金などの条件交渉」を行っていた場合、それらも非弁行為と認められる公算が高いのではないでしょうか。
また、退職届の作成を有償で請け負うなどの行為があれば、それも法律事務の一環と認められる可能性があります。
もうひとつ、退職代行サービス業界に与える影響も計り知れません。
今回の件でユーザーの減少や従業員の退職が多く発生すれば、アルバトロスという会社の存続が危ぶまれるかもしれません。
「モームリ」というサービスは、退職代行サービスの代表格。そこが倒産ということになれば、サービス全体が下火になるかもしれません。
退職代行サービスに否定的なぼくも、この流れは望みません。「選択肢は多いほうがいい」と思っているからです。
とにかく、今後の動向を細かく注視していきたいと思います。
正しい退職の手順
退職代行サービスがダメなら、どうやって退職すればいいの?
そんな声が聞こえた気がします。
でもね、とってもかんたんなんですよ。
いちばん揉めないのは、直属の上司(管理職)をメールなどで呼び出して、退職届を手渡すこと。
退職届の受理を拒否することは本来できないのですが、万が一、拒否された場合はメール、もしくは内容証明郵便で人事部宛に退職届を送りましょう。
ここで重要になるのが「送信or発信日を記録」しておくこと。
民法627条では、以下のように定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
要するに期間の定めのある、いわゆる「契約社員」でなければ、正社員でもアルバイトでもパートでも、退職の申入れから2週間で退職できるのです。
引き止めについて
以前からコラムでときどき書いていますが、本来は退職の意思決定に対して、企業側がどうこういう権利などありません。
だから、引き止め行為自体が違法なんです。
もちろん、強制力のない範囲で、説得やお願いをする権利はあります。でも聞き入れるかどうかはあなた次第です。
それでももし、無理やり引き止めようと会議室などへ呼ばれたら……「重要な案件なので、録音いたします」と相手に伝えてから、スマホのボイスレコーダーを起動させてください。
そして話し合いがうまくいかなかった場合は、こう伝えましょう。
「どうしても受け入れていただけないのであれば、民法627条にのっとり、本日から2週間をもって退職とさせていただきます」
普通であれば、ここまで言われて脅迫まがいの引き止めをしてくることはありえません。
よくあるトラブル
退職を強行しようとした場合、よくあるのが「次の人が見つかる(or育つ)まで、少し待ってくれ」と頼まれることと、「残りの給料は払わない」「退職金はなしだ」など金銭的な脅迫をしてくるケース。
しかし、安心してください。どちらも100%違法行為です。
とはいえ、なんの証拠もない状態では「言った・言わない」の水掛け論になること必至。
やはり打ち合わせは録音しておくに限ります。
録音時の注意点
まず、無断での録音は違法と判断される恐れがあります。そして、裁判では違法に収集された証拠を根拠にすることはできません。どれだけ相手の行動に非があっても不利になってしまうので、必ず「大事な打ち合わせなので録音いたします」と事前に伝えてから録音を開始してください。
また、このとき「録音してもいいですか?」とは聞かないほうがいいです。これだと、相手に断る権利が発生してしまいますから。
あくまで「録音いたします」と伝えるだけに留めましょう。
また、退職に関する打ち合わせでは、進行中の案件や独自の社内システムなど、社外秘の内容が話題に上る可能性があります。
そういった機密情報も録音することになるため、データの取り扱いには慎重を期しましょう。
万が一、流出などの事態になれば、損害賠償を請求されるかもしれませんので、気をつけてください。
どうしても退職できない場合
先ほども書きましたが、企業側が退職を拒否することはできません。
それでも、高圧的な上司のせいで、優しいあなたは退職を強行できない……そんなケースもあるかもしれません。
そのときは“弁護士事務所が運営”する退職代行サービスを頼みましょう。
「モームリ」などの民間代行業者(正社員で3~5万円ほど)に比べて、弁護士事務所は一般的に5~10万円と高額ではあるものの、あなたの貴重な時間を無駄にすることを考えれば安いものです。
まとめ:本当に“悪い奴”は誰だ?
退職代行サービスは、現代の若者から多くの支持を集めています。ということは、現代に“必要なもの”なんです。
今後の展開次第では、アルバトロスは社会的に“悪”と認識されるかもしれません。
そしてそのことは、ぼくも一切、否定しません。非弁行為を知らないはずがないので。
ただ、同じく“悪”な存在がありますよね。
本来、労働者の自由意志で決定できるはずの退職を素直に受け止めない、多数のブラック企業。こいつらはまぎれもなく、悪です。
でも、ぼくたちにも責任があります。
だって、退職代行サービス業者には容疑がかかったのに、ブラック企業の多くは野放しにされているじゃないですか。
なぜですか?
ぼくらが声を上げないからでしょう。
嫌なことは嫌だ。ダメなことはダメだ。その気持ちは声に出さないと伝わりません。
“NOと言える日本人”になりましょう!
| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |