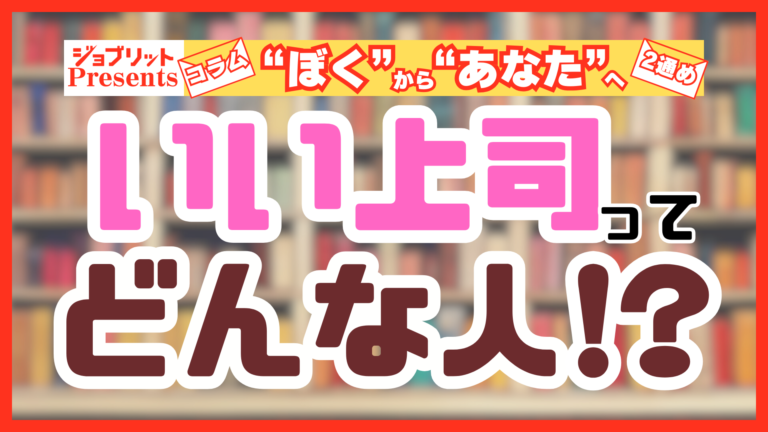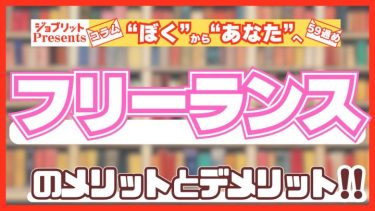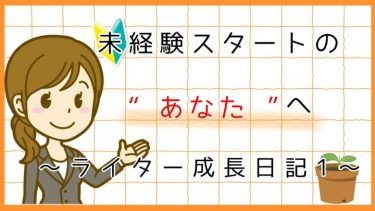ちょっと間が空いてしまいましたが、これからはまた毎週、仕事や会社、社会、その他ときどき関係ないものについて、コラムを書いていきます。
申し遅れました。わたくし、“魔王”と申します。偉いとかすごいとか強いとかではありません。これを書いている“ぼく”のいちばん好きな芋焼酎の銘柄っていうだけです。
ちなみに、以前にこのコラムをご覧になったことのある方にお伝えしておくと、当欄でずっと一人称「“ぼく”」で書いていた人間と同じです。ということは文章の拙さや読みにくさ、役立たなさも以前と同じです(笑)。
さて。間も空いたし、名前も変わったので、あらためてかんたんに自己紹介から。
ぼくはライターや雑誌/サイト編集といった文字周りの仕事を16年以上、続けている、これを読んでくださっている“あなた”よりはきっと少し(めちゃくちゃ?)年上の、平たく言えばおじさんです。
そんなぼくだからこそお若いあなたのお役に立てることがあるかもしれない。そう考えながらこのコラムを書いておりますので、今後とも末永くよろしくお願いいたします。
“今”、考える!「いい上司」ってどんな人?
このコラムを始めた当初、ぼくはこんなことを書いていました。
厳しい上司。優しい上司。仕事のできる上司。上司もさまざまですが、どんな人だと「いい上司」だと思ってもらえるのか、経験をも…
アドレスに打ち込んであるナンバーを見る限り、当コラム2本めの記事ですね。
当サイトでは比較的、多くの方にご覧いただくことができたコラムですが、あれから1年以上が経過した“今”、より具体的に書くなら令和7年7月2日現在では、ほんの少しだけ考え方が変わったこともあります。
コラム再スタートの意味も込めて、改めて「いい上司」について考えてみましょう。
「理想の上司」アンケート結果について
去年のコラムでも触れたリクルートマネジメントソリューションズ様がおこなったアンケート調査。
今回も、去年と同じくTOP7を掲載します。
ちなみに、コラム執筆タイミングの都合上、去年はさらにその前年となる2023年度の結果を掲載しましたが、今回はできたてほやほや。まさに最新といえる2025年度の結果でございます。
| 新入社員が上司に期待すること | |
| 相手の意見や考え方に 耳を傾けること | 49.7% |
| 一人ひとりに対して 丁寧に指導すること | 47.9% |
| 好き嫌いで 判断しないこと | 30.6% |
| よいこと・よい仕事を ほめること | 30.5% |
| 職場の人間関係に 気を配ること | 26.6% |
| 仕事に情熱を持って 取り組むこと | 22.6% |
| 言うべきことは言い、 厳しく指導すること | 22.0% |
(出典:リクルートマネジメントソリューションズ|2025年 新入社員意識調査【前編】)
結論から書くと、上位7項目の順位に変動はありませんでした。
ただ、個人的に予想外なこととして、「仕事に情熱~」が2年前から3%、「厳しく指導」が同4.5%と、どちらもそこそこポイントアップしているんですよね。
その分、減ったのは「好き嫌い」と「よいこと・仕事をほめる」の2つ。
順位を変動させるほどではないものの、それでも“熱血型”の上司を求める意識が、わずかながら復活しつつあるのでしょうか。
ぼくなりの「いい上司」はこんな人
ただ、去年の記事を書いたときと変わらない感想もあります。
それは、本当に嫌われるのはアンケートの上位2項目だけを見て安易に「やさしくしよう!」としたり、逆に熱血型がポイントアップしていると知って「やっぱり怒らなきゃだめだ!」てなったりする、“ブレブレおじさん”だと思っていること。
逆に言えば、上司自身がきちんと熱意や情熱、ときには厳しさを持ちつつも、それを押し付けるのではなく部下や後輩1人ひとりの声・姿勢に目と耳を傾けられる人が「いい上司」なのでしょう。
うん、こうして文字にしてみると、めちゃくちゃ当たり前のことですね(笑)。
でも、それが当然だと思います。だって、みんな「上司」なんてものに、そんなに期待してないでしょう?
当たり前のことを当たり前にやってくれれば、それで充分なんですよ。きっと。
ぼくの思う「いい上司」とは「いい職場」をつくる人!
さて、ここからが前回と変わったところ、というか追記したいところです。
というのも、ぼくは最近、こんな本を読んだんですよ。
>>チャーリー・マッケジー著、川村元気翻訳『ぼく モグラ キツネ 馬』
Amazonのリンクを貼っておきますけど、別にアフィリエイトとかではないですよ? ここから購入してもぼくやサイト運営元には1円も入らないので、安心してご購入ください(笑)。
そんなことはさておき、イギリスで大ベストセラーになったこちらの絵本。日本でもテレビ番組などで話題になっていたので、もしかするとご覧になったことのある方もいるかもしれません。
この本に、ものすごくいい言葉があったんです。
「(この本の)ぼく」が『今までに言った中でいちばん勇敢な言葉は?』と「馬」に聞いたとき、返事は『“たすけて”』でした。
さらにつづけて「馬」は言います。
『たすけを求めることは、あきらめるのとはちがう。あきらめないために、そうするんだ』
ぼくはここを読んだときに、このコラムを書くと心に決めました。
リセット症候群について
いきなりですけど、現代っていわゆる「リセット症候群」が根付いじゃったと思いませんか?
これについては近いうちに単独で書きたいと思っているので軽く触れるに留めますけど、何かがあったときに「すべてをリセットしたくなっちゃう/しちゃう」ことですね。
そんな現状を考えると、馬さんが言っていた『いちばん勇敢な言葉は“たすけて”』って、まさに現代人に響く言葉なんじゃないかなと思います。
「助けて」が言えたら、リセットなんてしなくてもいい。
「助けて」と言うのは“あきらめたとき”じゃなくて、むしろ“あきらめたくないとき”。
この本が世界中で共感を呼び人気を博した理由がここに詰まっている。ぼくはそう感じました。
そして現代人に響くということは、現代人が集まって働いている「会社」という組織内でも意識するべきじゃないかとも思ったんです。
上司がやるべきは「成功」ではなく「失敗」かも?
さきほど紹介したコラムとは別に、こちらのコラム(「ミスしてもいい!部下や後輩が成長できる職場の特徴を考える!」)でこんなことを書いていました。
(前略)ぼくに上司としてたった1つでもいいところがあったとするなら、やっぱりミスばっかりしていたことじゃないでしょうか。
上長がミスしまくって、頻繁に取締役に呼び出されてる。でもそのたびに「いや~、怒られちゃったよ」と笑いながら帰ってきて、その後も気にせずチャレンジを繰り返してる。
そんな姿を見ていれば、ミスを恐れることはなくなります(後略)
これを書いたときは、まだ『ぼく モグラ キツネ 馬』と出会う前だったんですが、今思うと、これって「“助けて”を言いやすい環境を作っていた」と言えなくもない……気がしませんか?
だってほら、ここでは「ミス」を題材にしているけどそれを「助けて」に置き換えるだけだし、当然のことながらぼくは何度となく部下・後輩たちに「助けて」と言いまくってましたし(笑)。
つまり、上司が失敗しまくる、助けを求めまくる。そうすることで部下や後輩たちも失敗を怖がらずにチャレンジできるし、誰かに「助けて」と言いやすくもなるのかもしれません。
「助けて」を言えるようになるたった1つのコツ
でも、この本を読んだ方の感想とかを見ていると、こんな風に思いました。
みんな「助けて」って言えないのかな? と。
もしそうなら、言えるようになる方法をお伝えすることはできます。
なにせこちとら、誰かれ問わず助けを求めまくってきた、いわばその道の大ベテランなんですから。まったく自慢になりませんね。
それはさておき、実際にどうすればいいのか。
かんたんです。
プライドを捨てればいいんです。
もっというならば、いっそのこと最初から自分自身にプライドなんて持たなければいいんです
持つべき“プライド”ってなんだろう?
それができれば苦労しねーよ!
そんな声が聞こえた気がするのは、勘違いでしょうか?
でもね、ぼくからすると“プライドを持つべきところ”の問題だと思うんですよ。
もう少し具体的に書くと、ぼくは「ぼく自身がいい原稿を書く」ことへのプライドなんて持っていません。
(「そもそもそんな実力ないだろ」という真因については、今だけスルーしてください。知っています。分かっています。それでもできないだけなんです)
でもぼくは「ぼくを含めたチーム全体でできるだけいい作品をつくる」ことに対しては、強いプライドを持っています。
つまり、プライドの当てはめ先とでも言いましょうか。主体が“自分”なのか“チーム”なのかと言う部分が、助けを求められるかどうかのポイントだと思っています。
大事なのは部下・後輩にも同じ意識を持ってもらうこと
ぼくはだいたい、3~4人で1つのチームを組んで仕事をしてきました。ライター1人にカメラマンも1人、そして進行管理が1人。あと、会社や仕事によってはカメラマン(撮影者)と編集者が別の場合もあるといった感じですね。
こういうのって、キャリアや役職ではなく、年齢でリーダー(っぽい人)が決まるんですよ。無能なぼくでさえ、35を超えたあたりからリーダー的な役割を押し付けられることが増えました。
そんな環境でぼくだけが「助けて」と言っていても、単なる上司・先輩の横暴ですよね。とてもじゃないけど、理想的な環境ではありません。
ぼくも若手も部署違い(進行管理だけは厳密に言えば別部署でした)の人も遠慮なく「助けて」と言えなきゃ意味がない。
あくまで無意識的に、無能なぼくが誰よりも先に・頻繁に助けを求めた結果、ぼくのチームは「助けて」が言いやすい環境になったのかもしれません。
ということは。
若手が1人で抱え込んだあげく、ある日突然退職届が送られてくる。そんな状況に悩んでいる方は、まずご自身が周囲に対して積極的に助けを求めてみてはいかがでしょうか。
コツはたった1つ。プライドを捨てる。というよりも、プライドの主体を変えてみること。
自分が、ではなくチームとして最大の成果を得るために、助けを求めたり求められたりすればいいんです。
まとめ:うまくいった理由は結局……
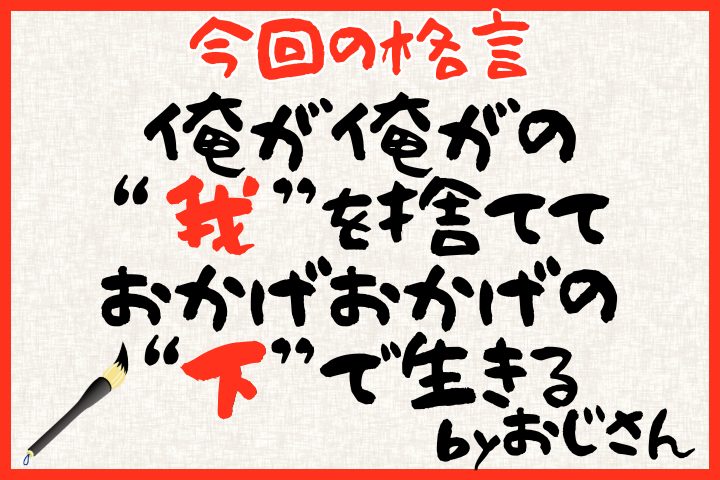
ぼくが無能だったからこそ、うまくいくこともあった。今回の仮説が正しいとすれば、そんな結論になるのかもしれません。
それなら、ぼくと同じことに悩んでいる方、全員にとって、非常に勇気づけられる事象とも言えるのではないでしょうか。
ただ、ここまで書いてきた今、正直に思うことが1つあるんです。
結局のところ、ぼくの周囲の人間は優しくて優秀な人ばかりだった。そのおかげのほうが、圧倒的に大きいんじゃないかなあ(笑)。
それでも、そんな人たちがぼくを助けてくれたことの事実は動かないので、多少なりとも参考にはなると信じて筆を置こうと思います。
じゃないと、ぼく自身が悲しくなっちゃうしね。
ぼくのケースは特殊ですけど、本来は業務経験の浅い若手が助けを求めることが多いはず。
だからこそ若手が声を上げやすい環境をつくっていただきたい。これだけは本心からお願いしたいところです。
| \学歴・経験不問の求人は/ \『ジョブリット』で検索/ |